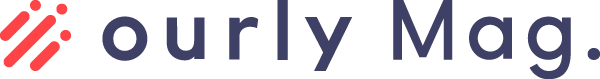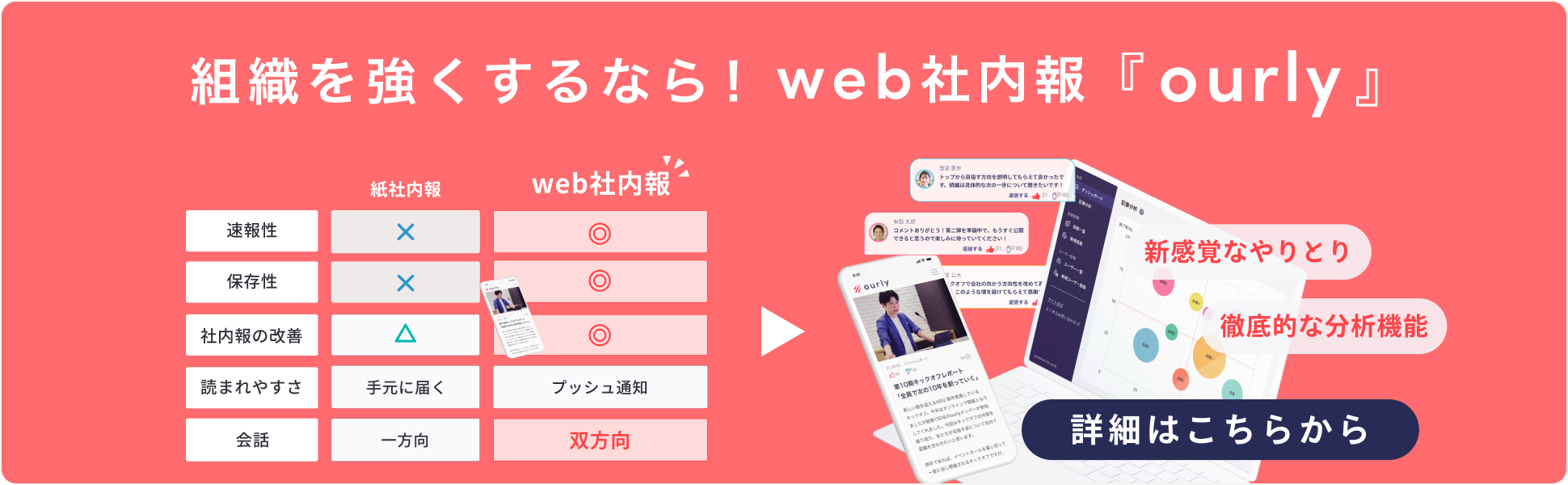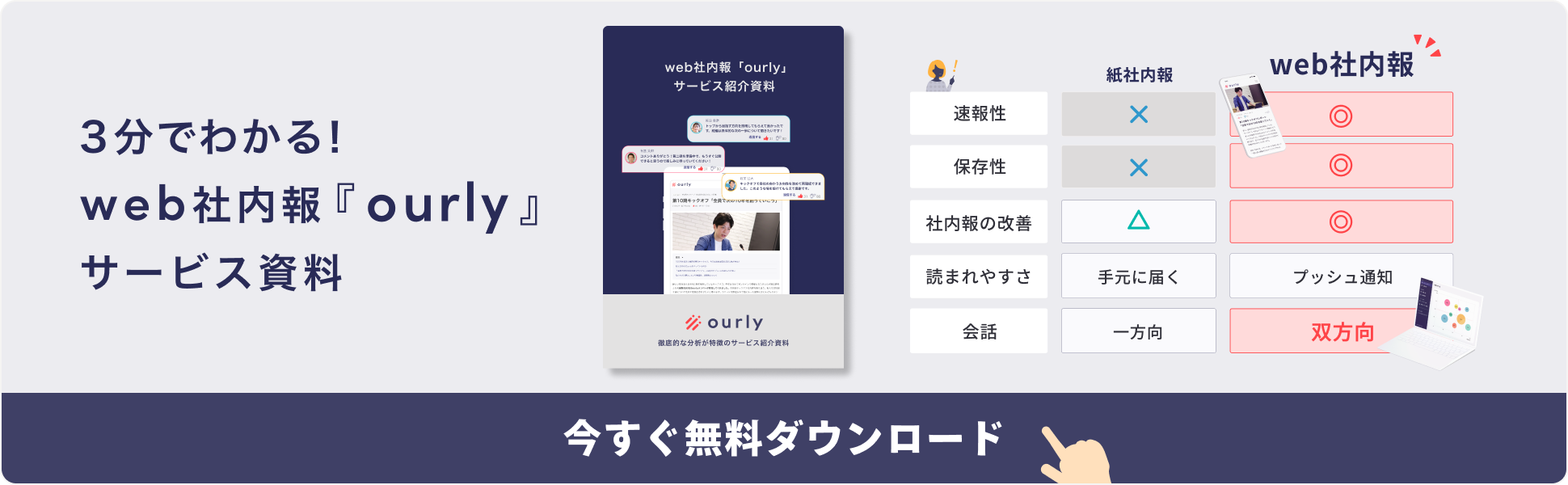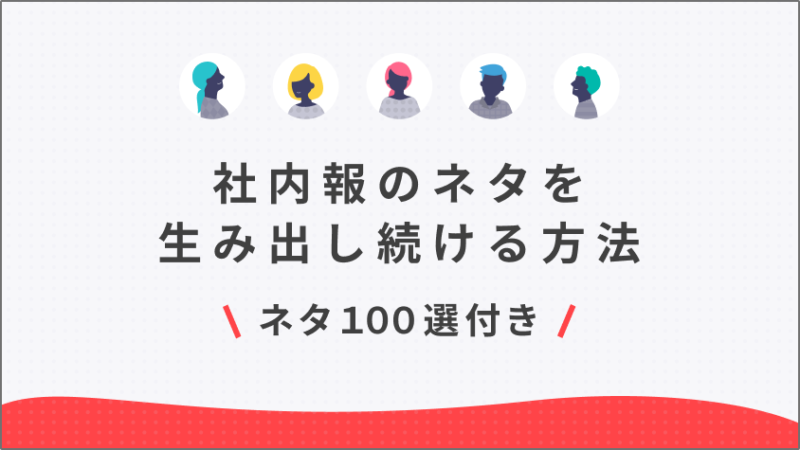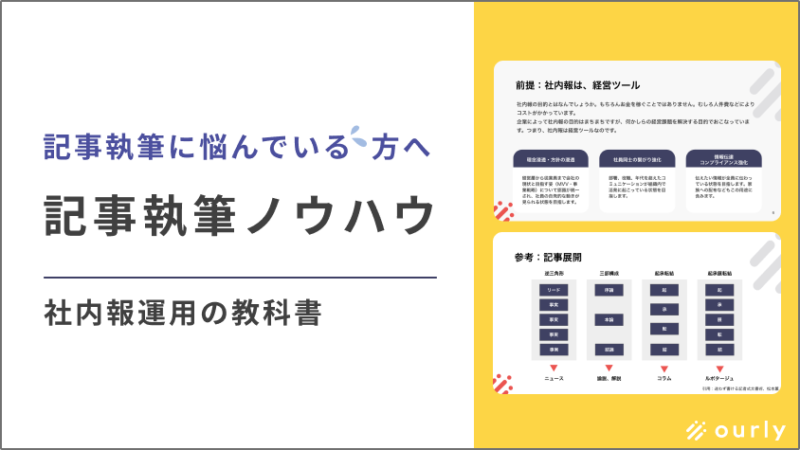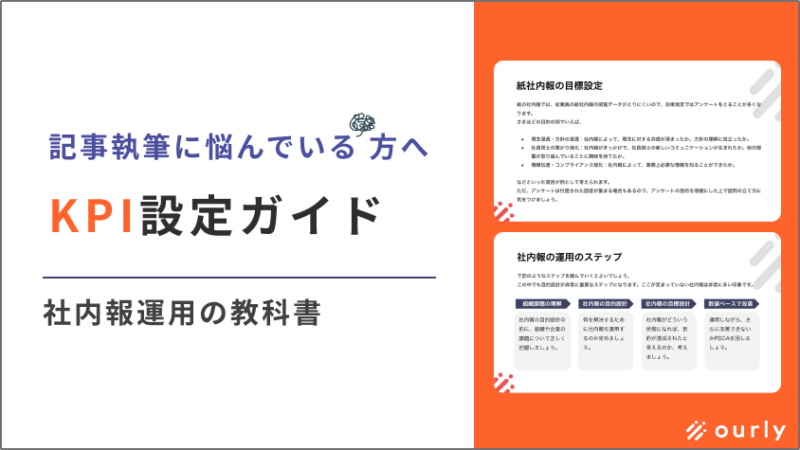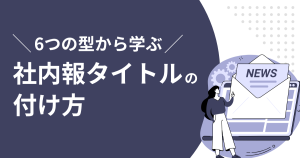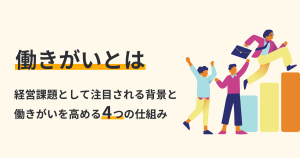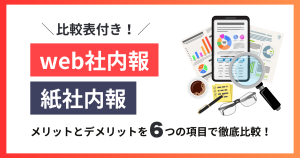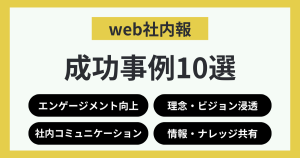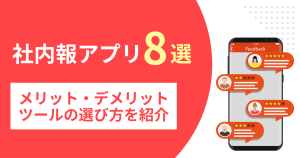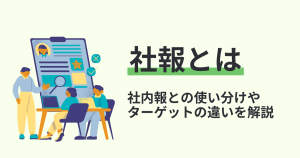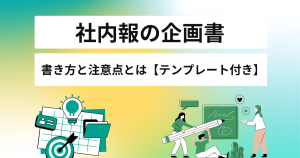外発的動機づけとは?メリットと限界、内発的動機づけに繋げる方法

外発的動機づけとは、従業員のやる気を引き出すモチベーションが外部からもたらされる状態のことを指します。例えば金銭的報酬や昇格といった、客観的に見てもわかりやすい仕組みが代表的です。
近年、「働き方改革」や「テレワークの普及」によって従業員の働きやすさは向上しつつある一方で、「仕事に対するやりがい」や「仕事自体への興味・関心」はむしろ低下しているという調査結果も報告されています。こうした状況で、短期的な外部インセンティブを活用する企業は増えていますが、外発的動機づけだけでは限界があるのも事実です。
本記事では、外発的動機づけのメリット・デメリット、内発的動機づけとの違いや移行の仕方に加え、外発的動機づけに潜むリスクや限界についても解説します。企業・組織が長期的にエンゲージメントを高めるための参考にしていただければ幸いです。
外発的動機づけとは
動機づけには、主に以下の2種類があります。
・外発的動機づけ:外部からの報酬(昇給・賞与・賞品)やペナルティ(評価低下・罰金など)によって動機が生まれる
・内発的動機づけ:興味・関心や成長意欲など、本人の内面から湧く動機によって行動する
外発的動機づけは、「○○をすればご褒美」「○○をしなければペナルティ」という形でシンプルに行動を促せる利点があります。しかし、こうした外的要因によるモチベーションは、長期的には持続しにくいという課題があり、内発的動機づけにつなげる工夫が不可欠です。
内発的動機づけと外発的動機づけの違い
内発的動機づけについて、また外発的動機づけとの違いについては下記の記事をご覧ください

外発的動機づけのメリット
外発的動機づけには、特に短期間で行動を喚起したい場面で、以下のようなメリットがあります。
・シンプルな方法なので誰にでも働きかけやすい
・短期間で効果が表れやすい
シンプルな方法なので誰にでも働きかけやすい
外発的動機づけは、「何をすればどうなるか」が明確な仕組みです。
たとえば「今月中に契約を3件獲得すれば、報奨金を支給する」といったルールは、誰にとっても理解しやすく、行動につながりやすいものです。
また、業務への主体性が見られない従業員に対しても、「行動すれば評価される」仕組みとして有効です。
実際、営業部門で「チーム目標達成でランチ会を実施」といったインセンティブを導入した企業では、若手社員の参加率や報告頻度が目に見えて改善したという例もあります。
このように、全社員を対象にした公平かつ明確なルール設計が可能な点が、外発的動機づけの実践上の強みです。
短期間で効果が表れやすい
報酬やペナルティを活用する外発的動機づけは、「今すぐ行動を起こしてほしい」場面に適しています。
たとえば、繁忙期やプロジェクトの山場で「今週中に作業が完了したら、代休+手当を支給」といった形で導入すれば、集中力を高める効果が期待できます。
また、ある製造業の事例では、「品質チェックの精度が一定基準を超えた場合に即時報酬を支給する」制度を導入した結果、チェック精度の向上が2週間以内に見られたという実績もあります。
短期的な成果が求められる場面では、即効性のある動機づけ施策として活用可能です。
外発的動機づけのデメリット・限界
一方で、外発的動機づけには以下のような注意点やリスク、そして「限界」が存在します。
・効果が一時的になりやすい
・内発的動機づけで働く従業員に悪影響を与える可能性
・モラルハザードやチームワーク低下などの副作用
・「働きやすさは上がっているが、やりがいは下がっている」状況における限界
効果が一時的である
外発的動機づけの代表的な注意点は、「慣れ」によって効果が薄れてしまうことです。
たとえば、営業目標の達成に対して月ごとに報奨金を設定した場合、当初は高いモチベーションを引き出せても、数ヶ月後には「いつもの報酬」として認識され、刺激としての効果が弱まることがあります。
また、インセンティブを下げたり廃止したりすると、「やる気がそがれる」「評価されなくなった」と感じる社員が出てくることも。実際にある企業では、報奨金制度を縮小した際に離職率が上昇した事例も報告されています。
このため、導入時には以下のような運用設計が必要です。
・報酬を一定期間ごとに見直す(例:四半期ごとに内容変更)
・金銭的報酬に偏らず、表彰・学習機会などの非金銭的インセンティブも組み合わせる
・成果基準だけでなく、プロセス評価を一部取り入れる
「成果報酬は永続的ではない」という前提で、長期的に継続できる制度設計や、報酬・評価の内容を定期的に見直す取り組みが欠かせません。
内発的動機づけで働く従業員へ悪影響を与える可能性
もうひとつ見落とされがちなのが、もともと仕事への興味・成長意欲で動いている従業員に悪影響を及ぼす可能性です。
たとえば、自己成長のために新しいプロジェクトに取り組んでいた社員が、急に「この業務はやれば手当が出ます」と言われた場合、「報酬のためにやっている」と感じるようになり、当初の情熱が失われることがあります。
これは「アンダーマイニング効果(過剰な外的報酬が内発的動機を損なう現象)」としても知られています。とくに、自律的に成長してきた中堅社員や、プロフェッショナル志向の高い若手に対しては、細心の注意が必要です。
実務では以下のような工夫が効果的です。
・内発的動機づけの強い層には、報酬よりも「権限拡大」や「裁量のある業務」を提供する
・インセンティブ制度の対象を限定的にする(例:新人育成、習熟度が安定していない領域など)
・制度導入前に、従業員アンケートや小規模な試行導入で反応を確認する
すでに高いモチベーションを持っている人に、無理に外発的動機づけを適用しない判断力も、人事には求められます。
モラルハザードやチームワーク低下などの副作用
外発的動機づけのインセンティブは、不正行為や過度な競争を生むリスクがあります。導入時には、行動面やプロセス評価も含めてチェックする体制を整えることが重要です。
・不正リスク:成果報酬の達成を急ぐあまり、不正な報告や手段が横行してしまう。
・協力の阻害:個人報酬や個人ノルマを強調しすぎると、チーム内の情報共有が滞り、協力関係が崩れる可能性がある。
「働きやすさは上がっているが、やりがいは下がっている」状況における限界
近年、ワークライフバランス向上やリモートワークの普及で物理的な「働きやすさ」は確かに改善されている一方で、「仕事に対する主体的なやりがい」や「自己成長実感」は下がりがちだという調査結果が複数報告されています。
こうした背景下では、一時的な金銭的インセンティブだけでは根本的なエンゲージメント向上にはつながりにくいという点が大きな課題です。
外発的動機づけは、あくまで「最初の一歩」を踏み出すきっかけとして活用し、やりがいや成長意欲を育む仕組みを併せて検討する必要があります。
外発的動機づけから内発的動機づけへ
外発的動機づけをきっかけに、従業員が「もっと成長したい」「新しいことに挑戦したい」と思うようになれば、やがて内発的動機づけが引き出される可能性があります。こうした好循環を「エンハンシング効果」と呼びます。
ただし、報酬や評価を与えるだけでは逆効果となるケースもあるため、個別の状況や従業員のタイプに合わせた制度設計が求められます。
外発的動機づけを活用して内発的動機づけを高める方法
金銭的報酬
金銭的報酬は、働いた分のお金をもらえるという、シンプルで効果的なモチベーションの方法です。目に見える形での報酬なので、短期的にはやる気を引き出すのに有効ですが、使いすぎると「お金がもらえないと動かない」といった考え方が強くなり、仕事の楽しさや成長への意欲が薄れてしまうことがあります。
リクルートでは、社員が年に一度の連続休暇を取ると、5万円の奨励金が支給されます。このお金は「頑張ったからご褒美」というより、「休むことに対する支援」として渡されます。
こうすることで、金銭的報酬が仕事のやりがいを奪うことなく、休養と仕事のバランスを保ちつつモチベーションを高めています。
言葉での称賛・表彰
言葉での称賛や感謝の言葉は、最も簡単にできて、しかも強力なモチベーションの源です。お金はかからないけれど、社員にとってはとても大きな意味があります。特に「何が良かったか」を具体的に伝えることで、社員の自信や意欲を高めることができます。
ザ・リッツ・カールトンでは、社員同士で「ファーストクラス・カード」を渡し合います。このカードは、他の社員の助けや貢献に感謝の気持ちを伝えるためのものです。
こうした感謝のカードは、社員同士のポジティブな文化を作り上げ、モチベーションを高める手助けになります。具体的な行動に対して感謝することで、社員は自分の仕事に誇りを持ち、もっと頑張ろうという気持ちになります。
フィードバックと成長支援
フィードバックは、自分がどれくらい成長しているかを知る大切な機会です。適切なタイミングでアドバイスをもらうことで、「自分はここができている」「次はこれをもっと改善しよう」といった前向きな意欲が湧いてきます。
また、成長支援をすることで、社員の仕事に対する意欲を持続させることができます。
ユナイテッドアローズでは、社員が自分の希望する職種に挑戦できる「社内公募制度」を導入しています。これによって、社員は自分のキャリアを自分で決めることができ、より積極的に成長しようという気持ちが湧きます。
また、定期的にフィードバックを行い、成長を実感できるようにサポートしています。
非金銭的インセンティブ・福利厚生
金銭報酬以外にも、社員の仕事の満足度やエンゲージメントを高める方法があります。福利厚生や働きやすい環境を整えることで、社員はより安心して働けるようになり、モチベーションが高まります。
特に「自分が大切にされている」と感じることが重要です。
株式会社ノバレーゼでは、社員が3年ごとに30日間のリフレッシュ休暇を取得できる制度を導入しています。長期の休暇を取ることで、社員はしっかりとリフレッシュでき、その後の仕事に対する意欲も高まります。
このような福利厚生は、金銭ではなく社員の心と体をサポートすることで、長期的なモチベーション維持に繋がります。
まとめ
外発的動機づけは、短期的に従業員のやる気を引き出すうえで非常に有効な手段ですが、以下のような限界と注意点を常に意識する必要があります。
・長期的には慣れや廃止によるモチベーション低下が起こりやすい
・過度な競争やモラルハザード、内発的動機づけへの悪影響が生じうる
・「働きやすさは増したが、やりがいが下がっている」現代では、外発的施策だけではエンゲージメント向上が頭打ちになりやすい
だからこそ、内発的動機づけと組み合わせた制度設計が不可欠です。報酬や評価を「単なるご褒美」ではなく、「成長や学習の機会」「権限や裁量を広げるチャンス」と結びつけることで、従業員のエンゲージメントを持続的に高められます。
最終的には、組織のビジョンやミッションを共有し、一人ひとりが主体的に活躍できる文化づくりを目指すことが重要です。